KB-402پEEK-402 ƒNƒ‰ƒVƒG نں蔯نن“’ ƒGƒLƒXچ×—±
 ƒNƒ‰ƒVƒG–ٍ•iپiƒJƒlƒ{ƒE–ٍ•iپj »
پلˆم–ٍ•iپâ
ƒNƒ‰ƒVƒG–ٍ•iپiƒJƒlƒ{ƒE–ٍ•iپj »
پلˆم–ٍ•iپâ
•إ“à–عژں
ƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پBژتگ^‚حڈمٹC‚جٹX•ہپBڈ¤•iڈî•ٌ
 (Mainly treatment) (Mainly treatment)ٹج’_ژ¼”M“ء‚ة‰©لtپi”畆پE–ع‚ج‰©گُ‰»پj‚ً’و‚·‚éٹج’_“¹Œnژ¾ٹ³پiژ¼”M‰©لtپj |
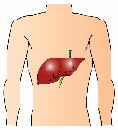


 •ûچـگà–¾ »پi‚«‚«‚ك‚ج”é–§‚ضپj
•ûچـگà–¾ »پi‚«‚«‚ك‚ج”é–§‚ضپj
|
پœٹج‰ٹپA“ء‚ة‰©لt‚ج‚ ‚éژ‚ة‚و‚—p‚¢‚ـ‚·پB‹¹‹ê‚µ‚پAŒû‚ھٹ‰‚«پA•ض”邵‚ؤ“ھ‚ةٹ¾‚ً‚©‚‚و‚¤‚بڈêچ‡‚ةژg—p‚µ‚ـ‚·پB پœ‘ج—ح’†“™“xˆبڈم‚جگl‚إپAŒûٹ‰پA”A—تŒ¸ڈ‚ح”نٹr“IŒy“x‚إپA•ض”éپAگSâ|•”‚ج–c–ٹ´پE•s‰ُٹ´‚ھ’ک–¾‚بڈêچ‡‚ة—p‚¢‚ـ‚·پB پœ–{•û‚حپAڈم• •”‚ب‚¢‚µ‹¹•”‚ج‰ٹڈا‚ً‹ژ‚èپA—ک”A‚ً‚ح‚©‚èپA‚آ‚¢‚إ‰©لt‚ًژ،‚·‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB پœ‰©لt‚ج–ٍ•û‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚إ‚·‚ھپA‰©لt‚ج‚ ‚é‚ب‚µ‚ةٹض‚ي‚炸—p‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‰©لt‚حگH“إپAگ…“إپA”M“إپi— ”Mپj‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚·پB–{•û‚حپuژ¼”M‚ج‰©لtپv‚ة‘خ‚·‚é‘م•\ڈˆ•û‚إ‚·پB پœ–{•û‚ج‚Rچـ‚ح‹¤‚ة‹êٹ¦‚جچـ‚إ‚ ‚èپAژ¼”M‚جژׂً“ٌ•ض‚ة‚و‚è”rں•‚µ‚ؤ•a‚ً‰ً‚µ‚ـ‚·پB |
| پy“K‰ڈاپz‰©لtپA‹}گ«ٹج‰ٹپA–گ«ٹج‰ٹپA’_‚ج‚¤‰ٹپAٹجچd•دپAƒlƒtƒچپ[ƒ[پA‚¶‚ٌ‚ـ‚µ‚ٌپAŒû“à‰ٹپAŒŒگ´ٹج‰ٹپAƒJƒ^ƒ‹گ«‰©لtپA‹}گ«گt‰ٹ |
|
پy’چپ@ˆسپz(Remark)
پ~ژc”O‚ب‚ھ‚çپA‘ج‚جژم‚ء‚ؤ‚¢‚é•û‚âˆف’°‚جژم‚¢‹•ڈط‚ج•ûپA—₦‚ج‹‚¢•ûپA‰؛—ںپiں•àbپj‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é•û‚حپA‹ضٹُپi‚«‚ٌ‚«پjپi•—p‚ً”ً‚¯‚éپj‚إ‚·پB |
|
پy”DگPپEژِ“û‚ج’چˆسپz |

| ڈ¤•i”شچ† | ‹Kٹi | –{‘ج‰؟ٹi | گإچ‰؟ٹi | گ”—ت | ƒJƒS‚ة“ü‚ê‚éپ« |
|---|---|---|---|---|---|
| k1577 | پiEK-402پj2.0gپ~42•ïپi2ڈTٹش•ھپj | 2,171‰~ | 2,280‰~پiگإچپj | ||
| k1575 | پiKB-402پj3.0gپ~28•ïپi2ڈTٹش•ھپj | 2,171‰~ | 2,280‰~پiگإچپj | ||
| k1576 | پiKB-402پj3.0gپ~168•ïپi12ڈTٹش•ھپj | 11,410‰~ | 11,980‰~پiگإچپj | ||
| k1578 | پiEK-402پj2.0gپ~294•ïپi14ڈTٹش•ھپj | 14,267‰~ | 14,980‰~پiگإچپj |

 “dکb’چ•¶ » “dکb’چ•¶ » |
 ‚e‚`‚w’چ•¶ » ‚e‚`‚w’چ•¶ » |
 ƒپپ[ƒ‹’چ•¶ » ƒپپ[ƒ‹’چ•¶ » |
 ’¼گع—ˆ“X » ’¼گع—ˆ“X » |
پœ‚²’چ•¶‚حپAڈم‹L”ƒ•¨ƒJƒSپA“dکbپAFaxپA‚ـ‚½‚حE-ƒپپ[ƒ‹‚إڈ³‚è‚ـ‚·پB  ‚²’چ•¶•û–@“™پEڈعچ× » ‚²’چ•¶•û–@“™پEڈعچ× »
|
گf’f‚جƒ|ƒCƒ“ƒgژں‚جڈاڈَ‚ھ‚ ‚é•û‚حپA–{•ûچـ‚ھ“K‚µ‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھ‘ه‚إ‚·پBپœ‰©لtپA”MپAڈ¬•ض•s—ک پœ‹¹‚©‚ç‚ف‚¼‚¨‚؟‚ج‚آ‚©‚¦ پœگS‰؛ل|پA• –پA•ض”é پœ”Mژׂھژ¼ژׂو‚è‹‚¢ |
نں蔯نن“’‚حپAژں‚جڈط‚ج•û‚ةچإ“K‚إ‚·پB
 ”畆•a‚ئژ¼”M » ”畆•a‚ئژ¼”M » نBˆفژ¼”Mپiژ¼”M‘j‘طنBˆفپj » نBˆفژ¼”Mپiژ¼”M‘j‘طنBˆفپj » ٹج’_ژ¼”M » ٹج’_ژ¼”M » ’†ڈإ‚ةژ¼”M‚جژׂھگN“ü‚µ‚½ڈêچ‡ » ’†ڈإ‚ةژ¼”M‚جژׂھگN“ü‚µ‚½ڈêچ‡ »
|
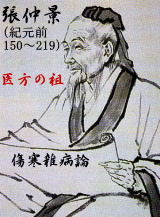
|
Œّ”\Œّ‰ت(efficacy)پiŒ’چN•غŒ¯ڈمپj Œûٹ‰‚ھ‚ ‚èپA”A—تڈ‚ب‚پA•ض”é‚·‚é‚à‚ج‚جژں‚جڈ”ڈاپFه@–ƒگ]پAŒû“à‰ٹ |
گ¬پ@•ھ’†ˆم–ٍپiٹ؟•û–ٍپj‚حپAژ©‘R‚جگA•¨‚â“®•¨‚ب‚ا‚ًŒ´—؟‚ئ‚µ‚½•،گ”‚جگ¶–ٍ‚ًڈˆ•û‚µ‚½–ٍچـ‚إ‚·پB–{–ٍ1“ْ—ت(6.0g)’†پF“ْ‹اƒ_ƒCƒIƒEپc1.0g “ْ‹اƒTƒ“ƒVƒVپc3.0g “ْ‹اƒCƒ“ƒ`ƒ“ƒRƒEپc4.0g ڈم‹L‚جچ¬چ‡گ¶–ٍ‚و‚è’ٹڈo‚µ‚½نں‚؟‚ٌنن“’ƒGƒLƒX•²––1400mg‚ًٹـ—L‚·‚éپB “Y‰ء•¨‚ئ‚µ‚ؤ“ْ‹اƒXƒeƒAƒٹƒ“ژ_ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€پA“ْ‹اŒ‹ڈ»ƒZƒ‹ƒچپ[ƒXپA“ْ‹ا“û“œپAٹـگ…“ٌژ_‰»ƒPƒC‘f‚ًٹـ—L‚·‚éپB |
‘gگ¬گ¬•ھژں‚حگ¬•ھگ¶–ٍ‚ج‰و‘œ‚إ‚·پBٹeگ¶–ٍ‚جڈعچ×گà–¾‚ةƒٹƒ“ƒN‚µ‚ـ‚·پB |
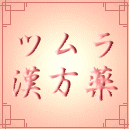
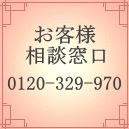


ژg—p•û–@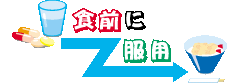 ’تڈيپAگ¬گl1“ْ6.0g‚ً2پ`3‰ٌ‚ة•ھٹ„‚µپAگH‘O–”‚حگHٹش‚ةŒoŒû“ٹ—^‚·‚éپB‚ب‚¨پA”N—îپA‘جڈdپAڈاڈَ‚ة‚و‚è“K‹X‘Œ¸‚·‚éپB
’تڈيپAگ¬گl1“ْ6.0g‚ً2پ`3‰ٌ‚ة•ھٹ„‚µپAگH‘O–”‚حگHٹش‚ةŒoŒû“ٹ—^‚·‚éپB‚ب‚¨پA”N—îپA‘جڈdپAڈاڈَ‚ة‚و‚è“K‹X‘Œ¸‚·‚éپB |
|
پyژg—pڈم‚ج’چˆسپz
(directions) پyگTڈd“ٹ—^پzپiژں‚جٹ³ژز‚ة‚حگTڈd‚ة“ٹ—^‚·‚邱‚ئپj 1. ‰؛—ںپA“î•ض‚ج‚ ‚éٹ³ژزپm‚±‚ê‚ç‚جڈاڈَ‚ھˆ«‰»‚·‚邨‚»‚ê‚ھ‚ ‚éپBپn 2. ’ک‚µ‚ˆف’°‚ج‹•ژم‚بٹ³ژزپmگH—~•sگUپAˆف•”•s‰ُٹ´پA• ’ةپA‰؛—ں“™‚ھ‚ ‚ç‚ي‚ê‚邨‚»‚ê‚ھ‚ ‚éپBپn 3. ’ک‚µ‚‘ج—ح‚جگٹ‚¦‚ؤ‚¢‚éٹ³ژزپm•›چى—p‚ھ‚ ‚ç‚ي‚ê‚â‚·‚‚ب‚èپA‚»‚جڈاڈَ‚ھ‘‹‚³‚ê‚邨‚»‚ê‚ھ‚ ‚éپBپn پyڈd—v‚بٹî–{“I’چˆسپz 1. –{چـ‚جژg—p‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚حپAٹ³ژز‚جڈط(‘جژ؟پEڈاڈَ)‚ًچl—¶‚µ‚ؤ“ٹ—^‚·‚邱‚ئپB‚ب‚¨پAŒo‰ك‚ًڈ\•ھ‚ةٹدژ@‚µپAڈاڈَپEڈٹŒ©‚ج‰ü‘P‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢ڈêچ‡‚ة‚حپAŒp‘±“ٹ—^‚ً”ً‚¯‚邱‚ئپB 2. ‘¼‚جٹ؟•ûگ»چـ“™‚ً•¹—p‚·‚éڈêچ‡‚حپAٹـ—Lگ¶–ٍ‚جڈd•،‚ة’چˆس‚·‚邱‚ئپBƒ_ƒCƒIƒE‚ًٹـ‚قگ»چـ‚ئ‚ج•¹—p‚ة‚حپA“ء‚ة’چˆس‚·‚邱‚ئپB 3. ƒ_ƒCƒIƒE‚جàb‰؛چى—p‚ة‚حŒآگlچ·‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚é‚ج‚إپA—p–@پE—p—ت‚ة’چˆس‚·‚邱‚ئپB |
|
 Œû“à‰ٹپA‰©لtپA‚¶‚ٌ‚ـ‚µ‚ٌپAƒlƒtƒچپ[ƒ[پAٹجچd•دڈا
Œû“à‰ٹپA‰©لtپA‚¶‚ٌ‚ـ‚µ‚ٌپAƒlƒtƒچپ[ƒ[پAٹجچd•دڈا 

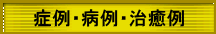
|
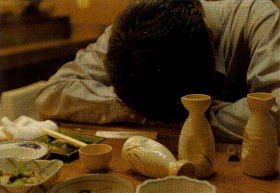
28چخ‚ج’jگ«پB پEŒ»‘م•a–¼پF“ٌ“ْگŒ‚¢ | |
 |
|
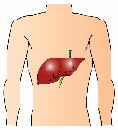
38چخپA’jگ«پA‹³ژtپB پEŒ»‘م•a–¼پF–گ«ٹج‰ٹ | |
 |
نں蔯نن“’—قژ—ڈˆ•û‚جڈذ‰î
ژں‚ج•ûچـ‚حپAژg—p–ع“I‚ھ–{•ûچـ‚ة”نٹr“I‹ك‚¢•ûچـ‚إ‚·پB‚ ‚ب‚½‚جڈاڈَ‚ئ‚ئ‚à‚ةپA”نٹrŒں“¢‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB|
| |
|
| |
|
| |
|
پœنں蔯نن“’‚حپAٹ؟•ûژ،—أ‚ج’ک–¼‚بŒأ“T‚إ‚ ‚éپuڈٹ¦ک_پvپu‹à“½—v—ھپv‚ًڈo“T‚ئ‚µ‚ؤ‚¨‚èپAŒأ—ˆ‚و‚艩لt‚ةڈـ—p‚³‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB–{چـ‚ح‚±‚جنں蔯نن“’‚ج—LŒّگ¬•ھ‚ً’ٹڈoپA”Zڈk‚µ‚½ƒGƒLƒX‚ً‚ج‚فˆص‚پAè÷—±چـ‚ئ‚µ•ھ•ï‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB پœ–{•û‚ح3ژي—ق‚جگ¶–ٍ‚©‚çگ¬‚èپA‚»‚جژه–ٍ‚إ‚ ‚éنں蔯نن‚ج–¼‚ً‚ئ‚ء‚ؤڈˆ•û–¼‚ئ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB |


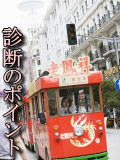
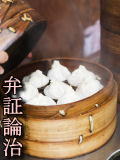
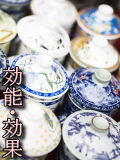

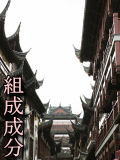







 è÷—±چـپcژUچـ‚ً—±ڈَ‚ة‰ءچH‚µ‚ؤ‘ه‚«‚³‚ً‘µ‚¦‚½‚à‚ج‚إپAƒTƒ‰ƒb‚ئ‚µ‚ؤ”ٍ‚رژU‚è‚ة‚‚ˆù‚ف‚â‚·‚¢–ٍ‚إ‚·پB—±‚ً“ءژê‚ب”ç–Œ‚إ•¢‚¢پA—n‚¯‚â‚·‚‚µ‚½‚à‚ج‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB–ٍ‚ھŒûپEگH“¹‚ة“\‚è•t‚‚ج‚ً–h‚®‚½‚ك‚ةپA‚ ‚ç‚©‚¶‚كگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ًˆù‚ٌ‚إŒûپEگH“¹‚ًژ¼‚点‚ؤ‚©‚çپAŒû‚ةگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ًٹـ‚فپA–ٍ‚ًŒû‚ة“ü‚ê‚ؤپAگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ئˆêڈڈ‚ةˆù‚فچ‚ق‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
è÷—±چـپcژUچـ‚ً—±ڈَ‚ة‰ءچH‚µ‚ؤ‘ه‚«‚³‚ً‘µ‚¦‚½‚à‚ج‚إپAƒTƒ‰ƒb‚ئ‚µ‚ؤ”ٍ‚رژU‚è‚ة‚‚ˆù‚ف‚â‚·‚¢–ٍ‚إ‚·پB—±‚ً“ءژê‚ب”ç–Œ‚إ•¢‚¢پA—n‚¯‚â‚·‚‚µ‚½‚à‚ج‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB–ٍ‚ھŒûپEگH“¹‚ة“\‚è•t‚‚ج‚ً–h‚®‚½‚ك‚ةپA‚ ‚ç‚©‚¶‚كگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ًˆù‚ٌ‚إŒûپEگH“¹‚ًژ¼‚点‚ؤ‚©‚çپAŒû‚ةگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ًٹـ‚فپA–ٍ‚ًŒû‚ة“ü‚ê‚ؤپAگ…‚ـ‚½‚ح‚¨“’‚ئˆêڈڈ‚ةˆù‚فچ‚ق‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB پq“ٌ“ْگŒ‚¢پr
پq“ٌ“ْگŒ‚¢پr پq”ٌA”ٌBٹج‰ٹپr
پq”ٌA”ٌBٹج‰ٹپr
![–]‹کOپi–k‹پj –]‹کOپi–k‹پj](http://www.hal.msn.to/objects_4/boukyourou001.jpg)

![ڈ¬گٍŒ³ژٌ‘ٹ‚جƒ`ƒƒƒCƒi•‚ئچ]‘ٍ–¯ ڈ¬گٍŒ³ژٌ‘ٹ‚جƒ`ƒƒƒCƒi•‚ئچ]‘ٍ–¯](http://www.hal.msn.to/objects_2/koizumi001.jpg)
